最近、詩に興味が出てきました。
メンタリストDaiGoさんのブログに、『1日1行読むだけで人生が変わる』という記事があり、
「難しいポエムを読むと脳機能が活性化したということです」と書いてあったのがきっかけでした。
そこからスタートして詩を読んだり、詩や詩人について調べたりしているうちに渡邊十絲子さんの『今を生きるための現代詩』という本を見つけました。
そこに
もともと、日本人は詩との出会いがよくないのだと思う。
大多数の人にとって、詩との出会いは国語教科書のなかだ。
と書いてあって、「本当だ!」と思いました。
”詩”と聞いて思い浮かべるのは教科書に載っていた詩で、「解釈して正しく理解しなければならないけど、できない」というイメージがついているなぁと。
そしてさらに
みんながみんなそんな専門的な読者である必要はないはずだ。もっと素朴に一字一句のありさまをじっとながめて、気にいったところをくりかえし読めばいいと思う。わたしはふだん自分のたのしみのために詩を読むときは、そのように読んでいる。
と書いてあったんです。
なるほど、でもそれってどういうこと?と思ったので、今回はこの本について書きます。
『今を生きるための現代詩』
内容<amazonより>
詩は難解で意味不明? 何を言っているのかわからない? いや、だからこそ実はおもしろいんです。
技巧や作者の思いなどよりももっと奥にある詩の本質とは?
谷川俊太郎、安東次男から川田絢音、井坂洋子まで、日本語表現の最尖端を紹介しながら、味わうためのヒントを明かす。
初めての人も、どこかで詩とはぐれた人も、ことばの魔法に誘う一冊。
あなたが変わり、世界が変わる。
印象に残ったところ
特に印象に残ったところは3つあります。
1.詩は謎の種
詩を読むということは、とても時間のかかるやっかいな作業です。
なぜなら、だれにでも通じることばではなく、安易には通じないことばだからです。
けれどもそのおかげで何年経っても読み飽きず、「知らない」「わからない」という特別な状態に長くいることができます。
詩は謎の種であり、その謎に接近しようとする試みの途上で実に色々なことを知り、感じ、考え、そして新たな自分が生まれます。
種からどんな芽がいつ出てくるのかを楽しみにしながら何十年もの歳月を進んでいきます。
2.詩は世界の手ざわりのひとつ
詩は、雨上がりの路面にできた水たまりに似ています。
路面の水たまりは無意識に踏まないように歩きます。
水たまりは儚いもので、しばらくすると消えてなくなります。
道路のアスファルトの表面にある微妙なへこみのかたちを、水たまりは教えてくれます。
水面に油膜がおちていて、ピンクと緑だけが強調されたようなふしぎな虹色に光っていることもあります。
そういう「世界の手ざわり」は、人間のコントロールからこぼれ落ちて、ただ人間をとりまく環境としてそこにあります。
人間は「手ざわり」に囲まれて生きていて、「手ざわり」から世界の正体を想像して日々を過ごします。
詩もまた、そういう世界の手ざわりのひとつです。
3.日本語の特性
日本語独特の特性があり、それをどうするかを日本語で書く詩人は悩むことができます。
まず表記について。
「バラ」「ばら」「薔薇」と書いた時、与える印象が全く違ってきます。
それから音韻について。
音の種類が少ないため、例えば「コーソー」という音に当てはまる熟語は「高層」「構想」「抗争」「後送」「広壮」のどれでもありえます。
そのため、「かける」ことができることばが多くなっています。
最後に、漢字について。
1つの漢字に音読み・訓読みがあり、どう読むかわからない場合があります。
これ以外にも、日本語の特性はまだまだあり、日本語の詩の可能性は広がっています。
「詩はわからないことが楽しい」ことを教えてくれる本
この本の中で一番強調されていたことは、「わからないことを楽しもう」ということだと思います。
「わからない」ことは「むずかしい」ですが、
「むずかしい」は「やさしい」より確実におもしろくてたのしい
と渡邊さんは言っています。
これからは、わからなさを楽しむために詩を読んでみようと思います!
余談
私が今気になっている詩人は「小笠原鳥類」さんです。
ネットで読める詩では「HOSE」という音楽ユニットのホームページに載っているものがすごく気に入っています。
あと萩原朔太郎も好きな感じ。
詩初心者なのでまだまだ模索中です。


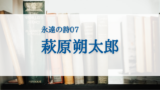


コメント